|
11月27日に発生した暴風雪に伴う66kV幌別線鉄塔倒壊に係る報告書の提出について |
2013年2月28日
12月3日、北海道産業保安監督部より「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について」を受領しました。
【指示文書の内容】
急速に発達した低気圧の影響による激しい暴風雪等により、送電鉄塔の倒壊などの送配電設備に被害が生じ、平成24年11月27日の早朝から30日にかけて、登別市を中心とした広い範囲で停電が発生した。
当該事象を受け、
- 今冬における再発防止策及びその実施計画
- 倒壊した送電鉄塔に関する建設当時の技術基準への適合状況の確認に関する事項
- 送電鉄塔の倒壊に関する原因分析
- 3を踏まえた再発防止策及びその実施計画
これらの再発防止策及び原因分析について、1については平成24年12月10日まで、2~4については平成25年2月28日までに報告すること。
今後、詳細を検討するとともに、再発防止策及び原因分析を速やかに取りまとめ、北海道産業保安監督部に報告いたします。
当社は、上記指示「1」に基づき、今冬における再発防止策及びその実施計画について、北海道産業保安監督部に報告いたしました。
今後は、報告した事項を着実に実施するとともに、残りの指示に対しても速やかに検討を実施し、取りまとめてまいります。
【今冬における再発防止策及びその実施計画に係る事項】
- 66kV幌別線に係る事項
- (1)仮設備による2回線化
- (2)移動発電機車による対応
- (3)送電線パトロールの強化
- 北海道全域に係る事項
- (1)緊急時対応の体制強化
今回のような暴風雪を伴う低気圧の襲来が予想される場合には、体制強化を図る。 - (2)送電線パトロールの強化
今冬の需給対策として、重要線路のパトロールの頻度を4回/1ヶ月程度(通常2回/1ヶ月程度)に増加し、パトロール強化を日常的に行っている他、気象状況が(1)と同様な場合には、パトロールを強化する。 - (3)復旧資機材の確保
当社及び施工会社保有の仮設鉄柱等、復旧用資機材の保有場所・数量を再確認し、事故発生時に迅速な対応を行えるよう準備する。 - (4)移動発電機車による対応
悪天候が予想される場合、移動発電機車の運転員、作業員を事前に確保・待機させるとともに、燃料手配の事前契約による迅速化を図る。 - (5)自治体等との連携強化
停電発生時においても、自治体等の関係機関との情報連携を確実に図れることができるよう事前の調整・協議を進め、現在のファクシミリ及び固定電話以外の情報伝達方法を整備する。
- (1)緊急時対応の体制強化
平成24年12月10日に報告した上記「1」に続き、本日、「2~4」の指示について、北海道産業保安監督部へ報告いたしました。
今後は、報告した事項を着実に実施し、再発防止に努めてまいります。
報告の概要は以下のとおりです。
1.「2.倒壊した送電鉄塔に関する建設当時の技術基準への適合状況」について
建設当時の技術基準への適合状況については、以下のとおりです。
今回倒壊した66kV幌別線No.29鉄塔は、昭和43年に建設され、「電気設備の技術基準(昭和40年制定)」に基づき設計されていた。
その後、北海道縦貫自動車道の建設に伴い、昭和55年に、隣接するNo.28鉄塔の移設建替工事を実施しているため、No.29鉄塔については建設当時とNo.28鉄塔の移設建替時で荷重条件が変更となっていた。
このため、建設当時の基準である「電気設備の技術基準(昭和40年制定)」及び移設建替時の基準である「電気設備の技術基準(昭和52年改正)」への適合状況について改めて検討した結果、いずれにおいても、鉄塔を構成する鋼材(ボルトを含む)、基礎コンクリート及び基礎支持力は、所定の強度を有しており、それぞれ当時の技術基準に適合していたことを確認した。
また、倒壊設備について、過去の保守状況の確認及び材料の強度試験を実施した結果、至近の巡視・点検では、鉄塔を構成する鋼材等の劣化やひび割れなど設備の機能に重大な影響を及ぼすような異常は確認されておらず、設備が健全であったことが確認された。また、材料の強度試験より、倒壊した鉄塔を構成する鋼材及び基礎コンクリートは、経年劣化による強度の低下がないことも確認した。
以上より、倒壊までは建設当時の技術基準に適合するように維持されていたことを確認するとともに、倒壊の原因は経年劣化ではないことも確認した。
2.「3.送電鉄塔の倒壊に関する原因分析」について
送電鉄塔の倒壊に関して、以下のとおり原因を分析しております。
- (1)鉄塔倒壊箇所では、午前4時から7時の間に、着雪が発達しやすい気温帯での集中的な降雪と平均風速10m/s~20m/sの風が継続する気象条件となり、電線に大きく着雪が発達した。
- (2)No.28~No.29間の送電線は、風向が直交していたため、上記のような大きく着雪が発達した反面、No.29~No.30間の送電線は、主に捻れ防止ダンパによるものと考えられる低減効果により、着雪量がNo.28~No.29間の50%程度以下に低減され、No.29鉄塔には着雪量のアンバランスが生じ、過大な張力差が発生した。
- (3)その後、当該箇所は、北西側のダム湖や西側の山岳地帯、南東方向の開放地形などの影響から、西北西方向に風向が変わると風が増速する特異な地形であったため、鉄塔倒壊箇所の平均風速が20m/s以上の強風になった。
以上の3つの条件が重なったことにより、鉄塔に大きな荷重が加わり、発生する応力が材料強度を超過し、鉄塔倒壊に至ったものと推定しました。
電線に大きく着雪が発達する気象条件と、風向と地形の影響による平均風速20m/s以上の強風が重畳した特異な気象状況下だったことが主因と推定されます。
なお、今回の鉄塔倒壊は、当該箇所において、今回のような3つの条件が重なる事象がこれまでになかったこと、全道においても同種の事象がなかったこと、他社でも同種の事象がなかったことから、知見が無く、事前に推定できない事象でした。
3.「4.3を踏まえた再発防止策及びその実施計画」について
今回の事象発生原因の推定結果という新たな知見を得たことから、これまでの当社の着雪における取り組みも踏まえ、同種事象発生の再発防止策を実施します。
- (1)鉄塔倒壊箇所(幌別線No.29鉄塔)
着雪量のアンバランス発生を防ぐことにより鉄塔の倒壊を防止できるため、No.28~No.29の径間に捻れ防止ダンパ取付けを行う(No.29~No.30間は捻れ防止ダンパを既に取付け済み)。
また、倒壊鉄塔の本復旧にあたっては、現行の「電気設備の技術基準(平成23年改正)」及び当社の着雪設計を満たす鉄塔と基礎に建替える。 - (2)その他箇所
以下の3つの条件が全て重なっている鉄塔の両側径間に、捻れ防止ダンパを取り付け、着雪量のアンバランスを解消する対策を実施する。- [1]1972年以前に建設された鉄塔
当社は1972年に発生した鉄塔倒壊を踏まえ、自主保安として当社着雪設計を1973年以降に導入しているため - [2]片側径間のみに捻れ防止ダンパを取り付けている箇所
他方の径間にも捻れ防止ダンパを取付け着雪時の荷重アンバランスを解消させるため - [3]がいし吊り型が耐張の鉄塔のみを対象とする
懸垂鉄塔では着雪量のアンバランスが発生すると、がいし連が重着雪側に振れることによる電線張力緩和効果が期待できるため
- [1]1972年以前に建設された鉄塔
- (3)再発防止策の実施計画
鉄塔倒壊箇所の本復旧(鉄塔建替)は、5月末目途で実施するとともに、その他箇所の対策については11月初旬を目途とし、可能な限り早期に完了させる予定。対象箇所は51基(82径間)とする。
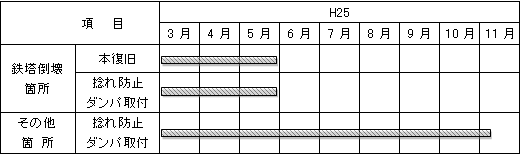
【添付資料】
66kV幌別線No.29 鉄塔倒壊について [PDF:457KB]